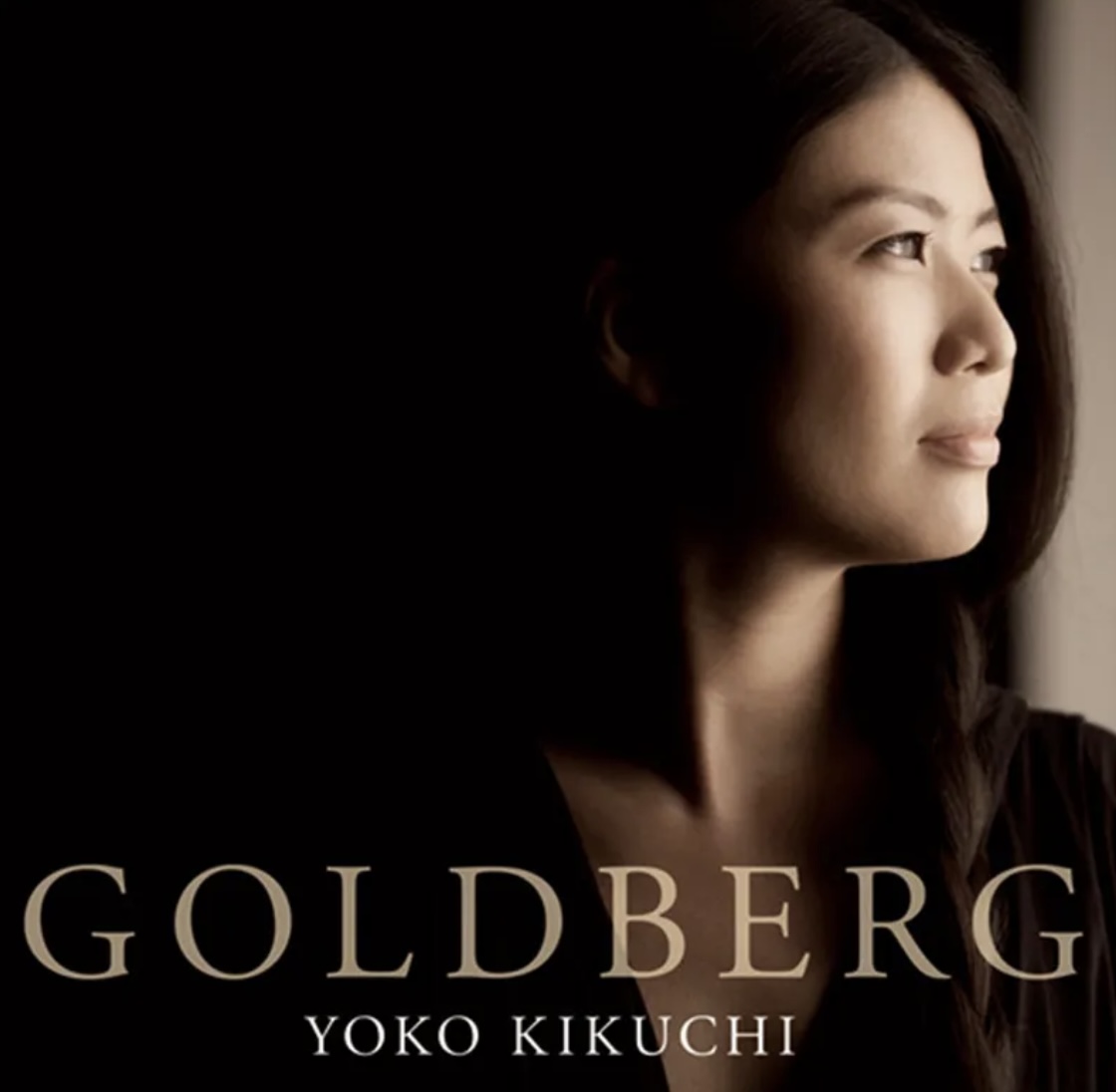佐賀県の海苔漁師さんが52歳からピアノを独習して、リストのラ・カンパネラを弾けるようになったという驚くべき話をご記憶の好楽家もいらっしゃるかと思います。今回あらためて調べてみたら、映画化されているんですね。何が言いたいかというと、誰にも「弾けるものなら弾いてみたい」という曲があるのではと私は思っていて、私の場合には、それがゴルトベルク変奏曲です。私の場合は、弾くのは無理なのですが。
この曲、以前は小林道夫先生が毎年クリスマスの時分に文化会館の小ホールで弾かれていて、そのコンサートに通うのが私にとって年末の大事な行事でした。ちなみに小林道夫先生の演奏は録音されていて、新旧二つの演奏を聴くことができます。いずれも、まさに「滋味、掬すべし」という演奏です。あと、私の世代だとカール・リヒターの演奏も忘れる訳にはいきません。急逝する直前の来日公演での演奏は、世評の高いアルヒーフ盤の鋭利な演奏に比べると、ゆっくり沈む夕陽のような味わいのものでした。これらはもちろん、チェンバロでの演奏。
ピアノによる演奏だと、なんといっても有名なのはグレン・グールドでしょうか。ただ、私は彼の鼻息(盛大に録音されてしまっています)が苦手で、もっぱら彼に大きな影響を与えたとされるロザリン・トュレックの演奏を愛聴してきました。これは実に素晴らしい演奏なのですが、意外に知られていないようですね。
そして、今回の菊池洋子さんの演奏会。この曲の実演をピアノで聴く機会は案外と少ないので、非常に楽しみにしつつ灼熱の夜にサントリーのブルーローズへ。
最後列を除いて、満席でした。 ピアノはスタインウェイ。
この曲は全部通すと80分を超えるため、真ん中の第16変奏のあとに休憩を入れることもあるのですが、菊池さんは全曲を一気に演奏。しかも暗譜。変奏曲の間はほとんどアタッカで弾かれたため、聴き手も集中力を試されることになりました。
それにしても、なんと素晴らしい演奏であったことでしょう。この曲をピアノで弾くということは、曲想の幅や奥行きを大幅に広げるということになるわけですが、その多彩さには驚くばかり。有名な第25変奏では、夜の香りが漂いました。菊池さんの技巧はすごいのですが、それはあくまでも表現の手段として用いられ、技巧そのものが前面に出ることは一切ありません。あくまでもバッハです。
80分、あっという間でした。来年もこの時期に弾かれるとのことですので、是非聴きたいと思った次第です。