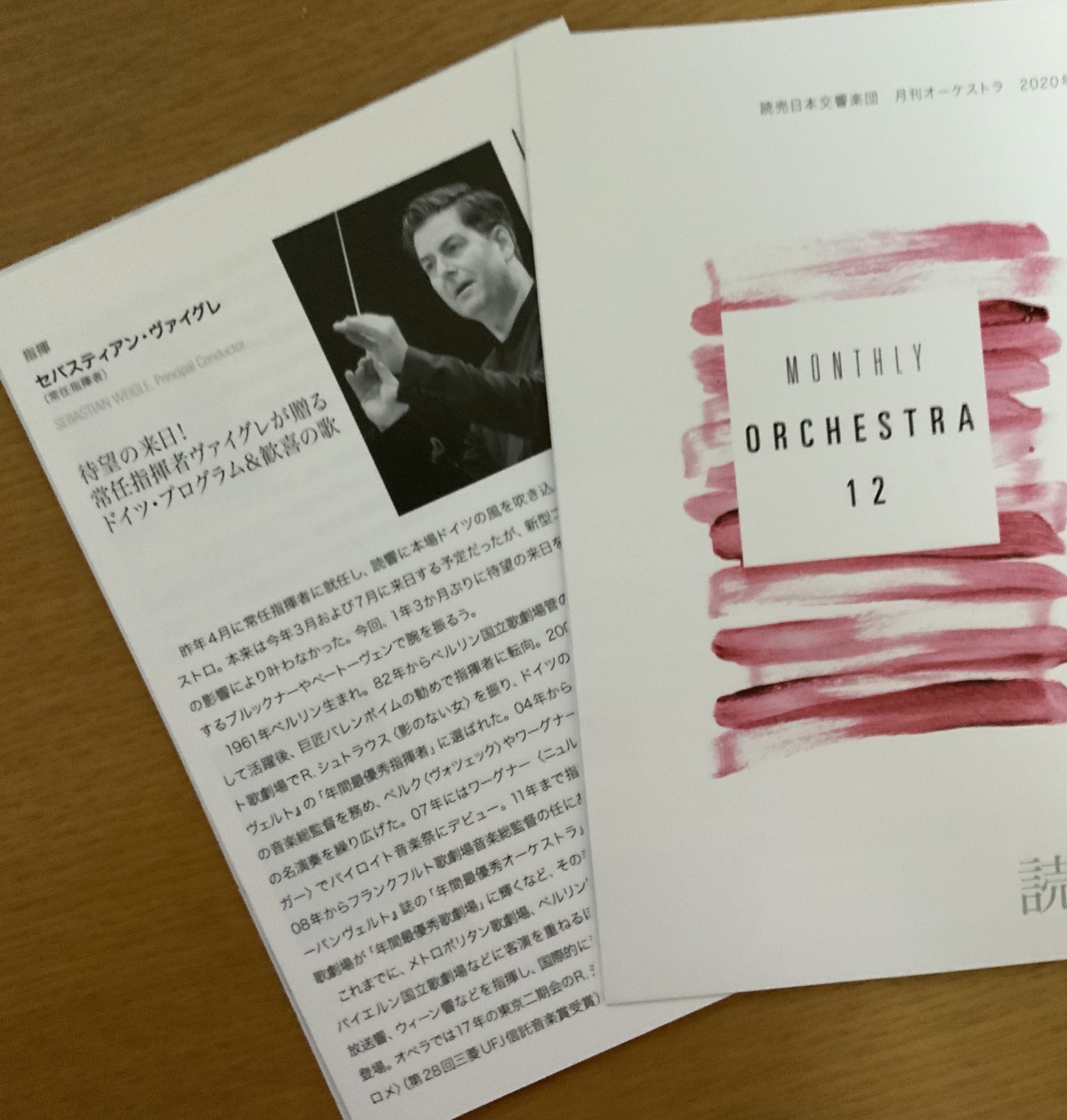現時点で外国から音楽家が来日する場合には14日間の自主隔離が義務付けられています。多忙な売れっ子の音楽家にとってスケジュールに2週間の空白を作るのは耐え難いこと。このため来日する音楽家はパッタリと絶えてしまっていました。しかし、コロナの欧州での第3波の拡大は止まるところを知らず、オーケストラもオペラもシャットダウン。日本に来れば聴衆の前で音楽ができるということで、敢えて来日を決断する方々も出てきました。
読響常任指揮者のセバスティアン・ヴァイグレもその一人。彼の場合には常任指揮者として義務感もあり、敢えて来日してくれました。
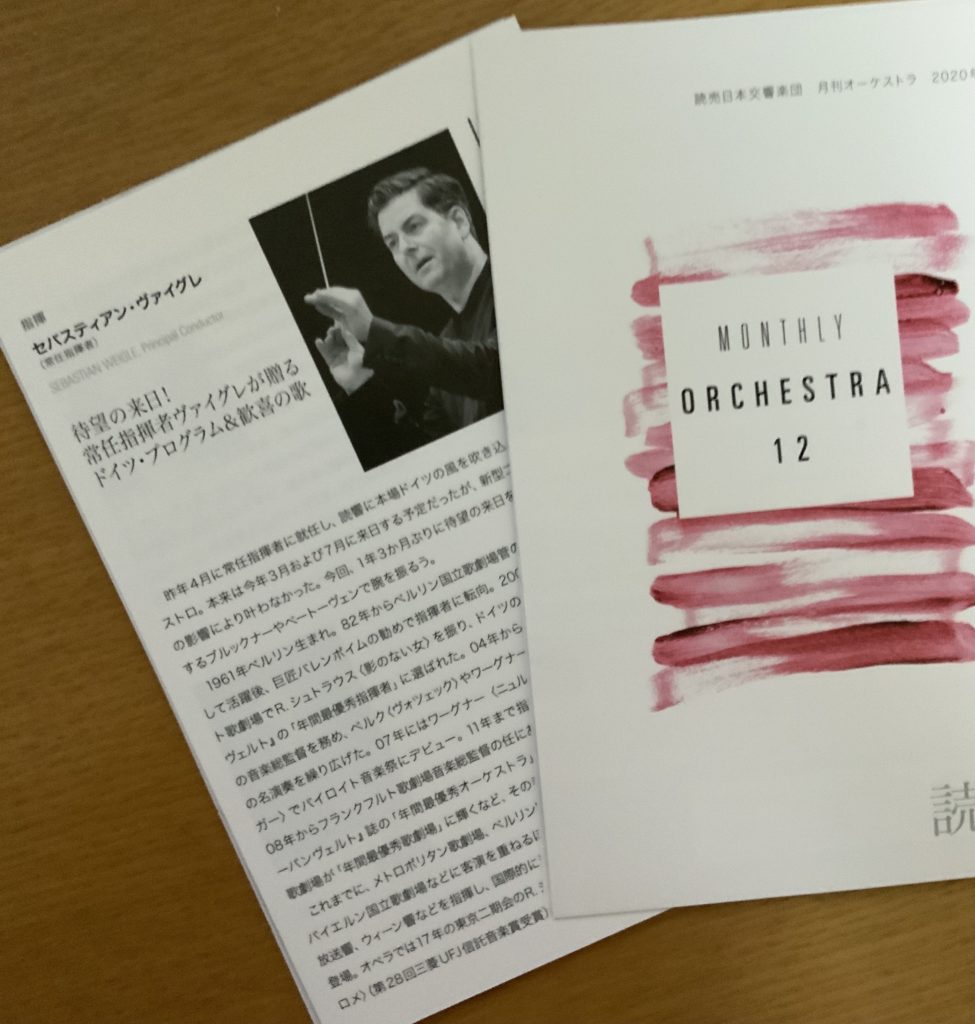
二週間の隔離期間をクリアし、まず臨んだのが今週水曜日(12月9日)のコンサート。曲目は前半がモーツアルトのピアノ協奏曲第25番(ソリストは岡田奏さん)、後半が目玉であるブルックナーの交響曲第6番。
モーツアルト:ピアノ協奏曲第25番
岡田奏さん、お名前は聞いていましたが実演に接するのは初めて。明るい音。15歳で渡仏し、10年フランスで研鑽を積んだというキャリアが示すように、プレイエルのピアノが似合うのではと思わせる音色。この世代の人ですので、技巧には全く文句の付け所がありません。素晴らしい。ヴァイグレもオケのサイズを絞り、ぴったりと付けてました。これは名演。
ブルックナー:交響曲第6番
ブルックナーの全10曲(0番含めて)の交響曲の中で、私はこの曲が一番好きです。中野雄先生には、「元永さん、それは変態だよ」と呆れられましたが。ですので、近年の日本でのこの曲の演奏は、全て聴いていると思います。まあ、そんなに演奏頻度が高いわけではありませんが。下野/広響、飯守/大フィル、カンブルラン /読響、大野/都響、上岡/新日フィルなどなど。海外だとブロムシュテット/シカゴ(シカゴでの初演!)、バレンボイム/シカゴも。
いままで最も素晴らしかったのは、演奏精度という点ではブロムシュテット/シカゴ、緻密さでは上岡/新日フィル。しかし、この日のヴァイグレ/読響は一段上の、たいへんな演奏でした。
この曲の白眉は第二楽章で、これはまあ誰が振ってもそれなりに美しいのですが、この日は第一楽章から陶然とする美しさ。こんなことは滅多にありません。
オケのサイズは10型。コントラバスは4本のみ。しかし、サントリーホールが「箱鳴り」するのではと思うくらいに豊かな響きでした。とにかく金管、とくにトロンボーンの鳴らし方が本当に巧み。これはドイツの歌劇場で育ったワーグナー指揮者でないと出来ない鳴らし方で、ホルスト・シュタインがそうでした。オルガンで曲想を練っていたと伝えられるブルックナーが想定していた響きかというと、もしかすると作曲意図を超えてしまっていたのかもしれません。(前述のブロムシュテット/シカゴでは、オルガン・トーンでした。ブロムシュテットの解釈と、それを実現できるシカゴ響の驚異的な金管群!)
テンポは早くもなく、遅くもなく。ただ、けっこうアッチェレランドをかけていく箇所があったのですが、不自然ではなく、音楽が迸り出る感じでした。
終演後は大拍手。私も立って拍手。
オケについて
読響、上手いですね。あと、スクロヴァチェフスキなどのブルックナー指揮者の薫陶を感じさせます。かつてはブルックナーといえば大フィルでしたけど、いまや読響なのではないでしょうか。
木管首席陣は敬称略で、倉田、蠣崎、藤井、吉田。蠣崎さんブラヴォー。そして何よりも立派だったのはホルンの日橋さん。まあお見事の一語に尽きます。低弦陣も本数が少ないことを全く感じさせないのが素晴らしい。
終演後のヴァイグレさんも会心の笑みでスタンディング・オベイジョンに応えていました。来てくださってありがとうございました。
カラヤン広場に出てみたら、今年はクリスマスのデコレーションがありませんでした。密を避けるということなんでしょうかね。